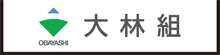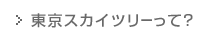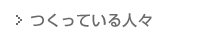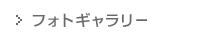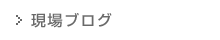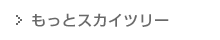新タワー建設工事事務所 副所長 服部道江
まず、生産設計という業務の内容について簡単に紹介してください。
みなさんご承知のように、建物を建てるときには設計図が必要ですが、いざ、実際の施工にあたってはさらに具体的で詳細な図面が必要になります。それが生産設計図であり、それを完成させるまでの検討、設計行為を総じて「生産設計」ということになります。
生産設計図は設計図及び設計者の意図に基づき作成されなくてはなりませんが、私たちはさらにそこに施工者としての情報を加えていくことになります。発注者のニーズの多様化、設計者の思いとともに設計内容が進化を続ける現状と日進月歩の施工技術、変化の著しいコスト状況の中、性能、品質確保という必須条件に加え工程、施工性、コスト削減といった事に関する施工者としてのアイディアも盛り込んでいかなくてはなりません。設計情報およびこれらがうまくマッチする場合は良いのですが、相反することがほとんどであり、それをバランスよく調整して、施工者はもとより設計者にとってももの造りの情報としてオーソライズされるよう纏め上げるのが私たちの仕事です。いわば設計と施工をつなぐ架け橋にも似た役目であると思っています。
生産設計図は設計図及び設計者の意図に基づき作成されなくてはなりませんが、私たちはさらにそこに施工者としての情報を加えていくことになります。発注者のニーズの多様化、設計者の思いとともに設計内容が進化を続ける現状と日進月歩の施工技術、変化の著しいコスト状況の中、性能、品質確保という必須条件に加え工程、施工性、コスト削減といった事に関する施工者としてのアイディアも盛り込んでいかなくてはなりません。設計情報およびこれらがうまくマッチする場合は良いのですが、相反することがほとんどであり、それをバランスよく調整して、施工者はもとより設計者にとってももの造りの情報としてオーソライズされるよう纏め上げるのが私たちの仕事です。いわば設計と施工をつなぐ架け橋にも似た役目であると思っています。
生産設計図を作る際、どのようなことに注意しますか?
繰り返しになりますが、ものを造るための情報、つまり設計情報と施工者としての必要情報を正確にまとめ上げて工事担当者に伝達することが業務の基本です。不整合、齟齬の無い生産設計を目指しています。また、当社ブランドを汚すことのないよう性能と品質の確保にも注意します。強度の確保、漏水、クラックの防止等については日常気をつけています。そしてもうひとつ、私は「宝物」と呼んでいますが、設計図の中にはお客さまにとっても施工者にとっても利益となる情報がたくさん隠れています。それらを拾い上げてアイディアとしてまとめ「提案」し、粘り強く関係者と「折衝」して「実行」に導くことを常に心がけています。
設計と施工の狭間で苦労もしますが、もの造り情報の発信源であり、VE(バリューエンジニアリング) ※と幅広い意味での利益確保の拠点であるという自負を持って業務に取り組んでいます。
設計と施工の狭間で苦労もしますが、もの造り情報の発信源であり、VE(バリューエンジニアリング) ※と幅広い意味での利益確保の拠点であるという自負を持って業務に取り組んでいます。
東京スカイツリーの現場に配属になると決まったときにはどんなことを感じましたか?
私が配属になると決まる前、設計図を目にした段階では、非常に興味深く面白そうだと思っていました。が、私が配属されると知ったとき、少し怖くなりました。なにしろ誰も経験したことのないものを造るわけですから、どんなところにどんな問題が潜んでいるのかわかりません。そんなことが頭をよぎって怖さが先にたったというのが本音です。
でも、実際に現場に入っていろいろな方と出会い、ダイナミックな工法に接する中で、今はスタッフ全員がそうであるように、私も誇りを感じながら仕事をさせていただいています。
でも、実際に現場に入っていろいろな方と出会い、ダイナミックな工法に接する中で、今はスタッフ全員がそうであるように、私も誇りを感じながら仕事をさせていただいています。
入社してからずっと生産設計にいらっしゃるのですか?
入社してすぐに生産設計部(当時は工務部工務課)に配属されました。その後、短い期間でしたが生産技術の部署で仮設の計画や見積りなどの業務を経て、工事係員として現場に配属され2物件、4年間程工事管理の業務を経験しました。これらの経験は今の生産設計の仕事におおいに役立っています。
東京スカイツリーは大林組の単独施工で行うわけですが、当社の強さはどんなところにあると思いますか?
これまで経験してきた中でいっそう強く感じるのは当社の"人の層の広さと厚さ"ということです。例えば、難しい問題が発生したときや新しいアイディアを必要とするとき、いつも同じ顔ぶれで打合せを行っていては、回答、解決策も出てこないし、なんら展開も進歩もありません。当社は、新しいことを始めようとするとき、想定外の問題が発生したときなど、いざというときにはその場面、場面により、適任のスタッフが登場してきます。人が人を育て、個性を伸ばす風土の中、色々な年代、部署の人間がいて、それぞれ経験、得意分野も知識の深さも様々ですから、その課題の内容やハードルの高さに応じた人材がいるわけです。こういった人の層の広さと厚さは、このプロジェクトの礎であり、今後も、大きな力となるのではないでしょうか。
最後に新タワーの完成を楽しみにしていらっしゃる方々にメッセージをお願いします。
一つの時代のモニュメントとして世界に誇れる作品になると思います。日本人すべてに見ていただきたいです。この時代の建設技術の集大成であり、その象徴としてずっと後世に残っていくものでもありますから。
※ VE(Value Engineering)とは、製品やサービスの「価値」を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」との関係で把握し、「価値」の向上をはかる手法です。
※ VE(Value Engineering)とは、製品やサービスの「価値」を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」との関係で把握し、「価値」の向上をはかる手法です。